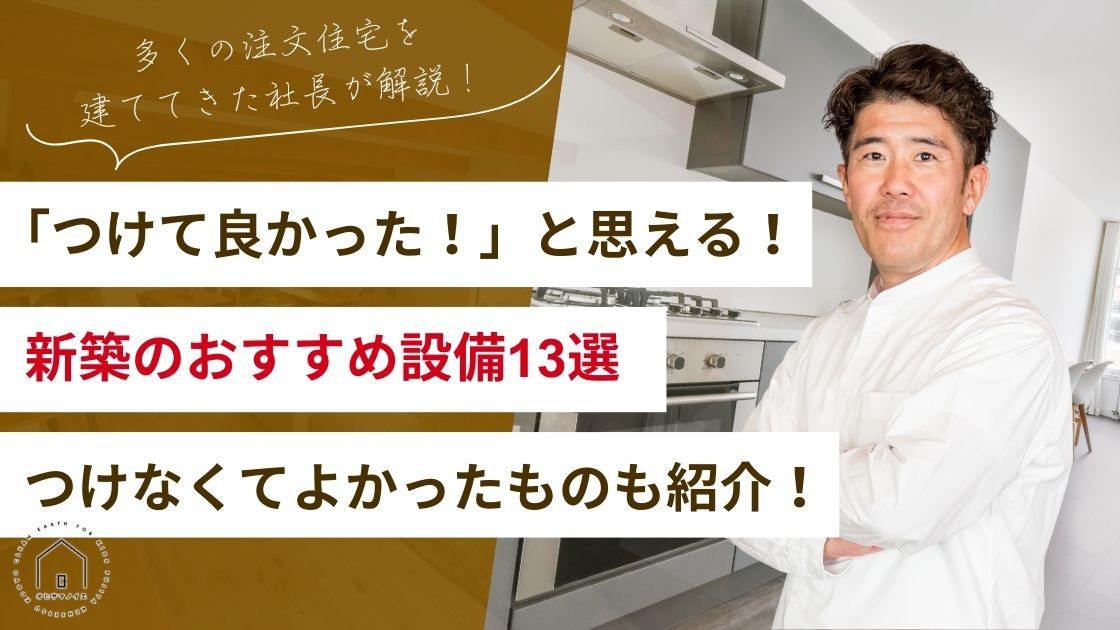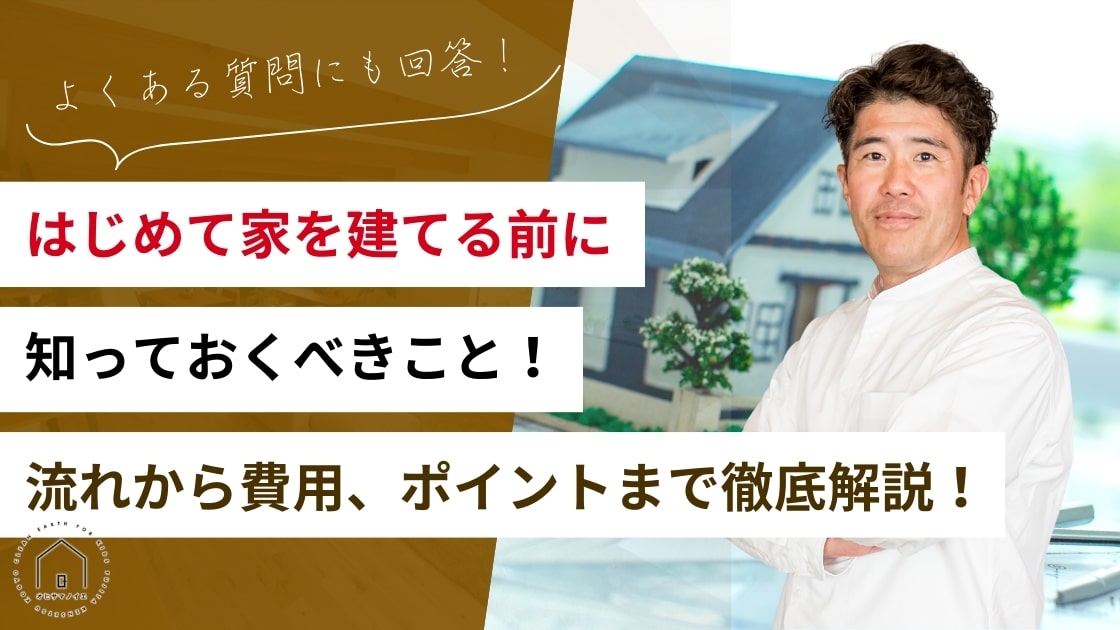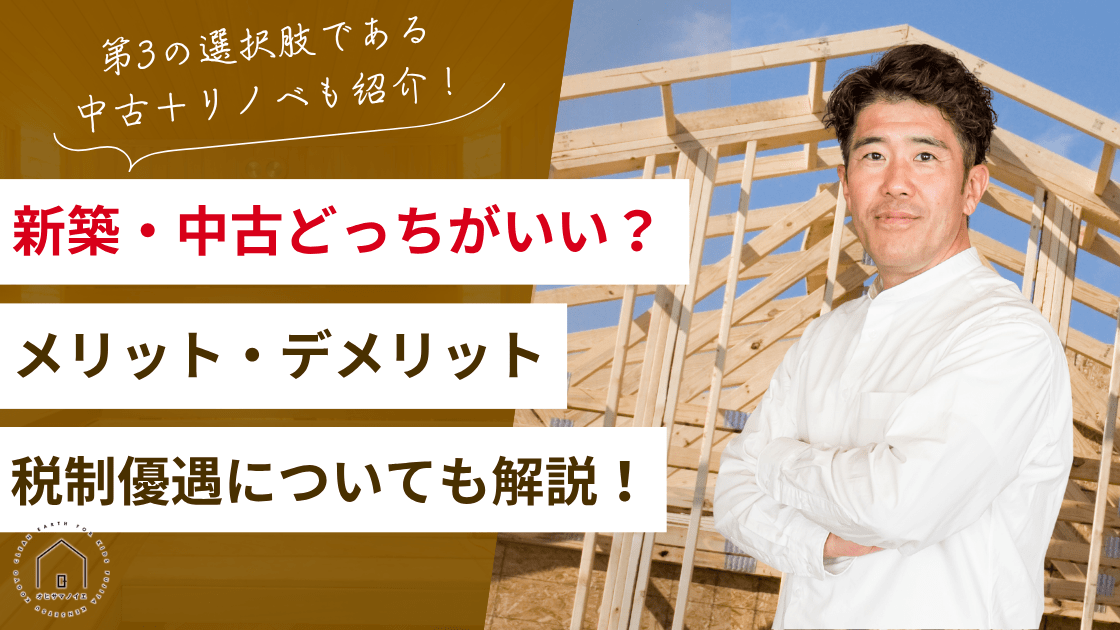
この記事では、あなたがどちらに向いているかフローチャートで一目でわかるように解説します。
また、新築と中古それぞれのメリット・デメリットや、第3の選択肢である中古をリノベーションについても解説します。
マイホーム購入は人生で最も大きな決断のひとつです。最初に「新築」か「中古」のどちらを選ぶかで、その後の資金計画やライフスタイルが大きく変わります。
この記事を読めば、あなたの予算やライフスタイルに合った最適な選択肢を見つけ、後悔のないマイホーム選びを進められるようになりますので、ぜひ参考にしてください。
「新築・中古 どっちがいいか」はあなたの優先順位で決まる
こちらでは、「新築・中古 どっちがいいか」はあなたの優先順位で決まるという内容を解説します。
あなたに最適なのは「新築」?「中古」?【診断フローチャート】
新築と中古、どちらが最適かはあなたの「優先順位」によって決まります。
多くのお客様と接してきて、よく重視されるポイントに基づいて、新築・中古の選択診断フローチャートを作成しましたので参考にしてみてください。

| 診断結果 | 特徴とメリット | デメリットと注意点 |
|---|---|---|
| 新築 | ・最新設備、高い耐震性・省エネ性能 ・きれいな状態からスタート ・住宅ローン控除など税制優遇が中古より手厚い ・当面大きな修繕・リフォームは不要 |
・価格は中古に比べ物件価格が高い ・資産価値は入居直後から価値が下がりやすい ・立地は郊外や新規開発エリアが中心になりやすい |
| 中古 | ・価格は新築に比べ物件価格が安い ・駅近や生活利便性の高いエリアに物件が多い ・リフォーム・リノベーションで好みを反映しやすい |
️ ・築年数によっては修繕や設備交換の費用がかかる ・入居前に不具合を細かく確認する必要がある ・新築に比べ優遇期間や控除額が少ない、または適用外 |
最終的には、予算・立地・新しさ・自由度・将来のリスク許容度など、ご自身の価値観に照らし合わせて決定することが重要です。
どっちがお得?「新築」と「中古」の総額・維持費を比較
「新築」と「中古」のどちらが「お得」かは、「保有期間」と「リフォームの有無・内容」によって変わります。
一般的に、初期費用と長期的な維持費を比較すると、以下のようになります。
| 大項目 | 項目 | 新築 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 初期費用 (購入総額) |
物件価格 | 高い(最新の設備、建材費、広告費などが含まれる) | 安い(新築に比べて2割〜5割程度安くなる傾向) |
| 諸費用 | 物件価格の約3〜10% (仲介手数料なしの場合が多い) | 物件価格の約6〜13% (仲介手数料が必ずかかることが多い) | |
| リフォーム費用 | 不要(注文住宅を除く) | 必要となることが多い(水回り、内装、断熱改修など) | |
| ランニングコスト(維持費) | 修繕・メンテナンス費 | 低い(最初の10〜15年は大規模修繕が不要なことが多い) | 高い(築年数に応じて設備交換や大規模修繕が早期に必要になる) |
| 光熱費(ランニングコスト) | 低い(最新の省エネ基準、高気密・高断熱性能が高い) | 高い(断熱性能が低い物件が多く、光熱費がかさみがち) | |
| 固定資産税 | 高い(当初3〜5年間は軽減措置あり) | 低い(新築より評価額が下がりやすい) | |
| 税制優遇 | 手厚い(住宅ローン控除の期間・控除額が中古より優遇される) | 限定的(控除期間・額が新築より短く少ない。耐震基準の証明など条件あり) |
【短期保有(5〜10年)なら中古が有利】
新築は初期の10年で資産価値が大きく下落する「新築プレミアム」が剥がれますが、中古はすでに値下がり済みのため、売却時の損失が少なく総支出が抑えられます。
【長期保有(20年超)なら新築も視野】
新築は初期費用が高くても、省エネ・税制優遇・低い修繕コストで総額を回収します。一方、中古は長期で複数回の大規模修繕が必要となり、初期費用の安さが相殺されてしまいます。
最終的なお得度は、「初期費用の差額」と「中古の築年数・状態(修繕回数)」を考慮するようにしてください。立地重視なら中古、手間とランニングコスト重視なら新築が目安です。
中古物件購入時に見落としがちな諸費用
中古物件は価格の安さが魅力ですが、新築以上に諸費用が複雑で、予算オーバーの要因になりがちです。
中古購入にかかる費用は、新築と比較して諸費用率が約1〜3%割高になる傾向があり、物件価格の7%〜10%(新築は通常5%〜7%)が目安です。
| 費用区分 | 見落としがちな項目 | 新築との大きな費用差 |
|---|---|---|
| 購入時 | 仲介手数料 | ・物件価格の3%+6万円(上限)がほぼ必ず発生(新築の売主直売では不要) ・諸費用の中で最も高額 |
| ローン諸費用 | ・数十万円〜数百万円 ・金利以外にローン保証料などがかかり、ローン商品で差が出る |
|
| 入居前・後 | 予備費 | ・リフォーム費の10%〜20%を確保必須 ・壁の裏の配管腐食など、隠れた不具合への追加工事費 |
| 修繕積立金 | ・中古マンションは値上がり傾向 ・大規模修繕前に一時金(賦課金)が徴収されるリスクがある |
特に中古では、仲介手数料に加え、リフォーム時の予期せぬ追加費用が予算を大きく上回ることもあります。見えないところに不具合が起こっているということも。
初期費用だけでなく、「リフォーム+諸費用+予備費」の合計で資金計画を立てることが重要です。
新築・中古のメリット・デメリット
こちらでは、新築・中古のメリット・デメリットについて解説します。
【新築】「誰も使っていない安心感」 vs 「価格と立地」
新築の魅力は、なんといっても「誰も使っていない安心感」と「高性能である」という2点です。
最新設備と高い耐震性・断熱性が保証され、故障リスクや初期の修繕費も抑えられます。「最新の快適性・高性能・安心の保証」を重視する方に向いています。
しかし、その代償が「価格と立地」で、新築は物件価格が高く、同じ予算では中古より狭くなりがち。
また、駅近などの好立地は少なく、郊外が中心で、購入直後の資産価値下落が早い点もデメリットです。新築は安心と快適性、中古は価格と利便性の高い立地を優先するかで選択することなります。
以下に新築のメリットとデメリットをまとめましたので、参考にしてみてください。
| 区分 | メリット(利点) | デメリット(懸念点) |
|---|---|---|
| 価格・費用 | ・税制優遇が手厚い(住宅ローン控除の期間・控除額が大きい傾向) ・最初の10〜15年は大規模な修繕費用が不要 |
・物件価格が中古に比べて高額 ・同じ予算で比べると立地や広さを妥協しがち ・資産価値の下落が早い(新築プレミアムが剥がれるため) |
| 安心感・性能 | ・誰も使っていない清潔な状態で新生活を始められる ・最新の設備・高性能(高断熱、高耐震)で快適性が高い ・法律に基づく長期の保証(瑕疵担保責任10年など)があり安心 |
・立地に制約がある ・駅近や都心などの人気エリアは中古が中心になりやすい |
| その他 | ・高性能によりランニングコスト(光熱費)が低い傾向 ・注文住宅なら間取りやデザインの自由度が高い |
・周辺環境が住んでみないとわからない(騒音、日当たり、近隣住民など) ・完成まで時間がかかる(注文住宅の場合) |
【中古】「立地の良さ」 vs 「見えない不安」
中古の最大の強みは新築では難しい駅近や利便性の高い人気エリアの物件を、価格を抑えて購入できる点です。加えて、実物をもとに周辺環境を事前に確認できる安心感もあります。
中古住宅は、「立地の良さ」と「価格の安さ」を最優先し、リフォームの手間や費用を許容できる方に向く選択肢です。
一方で、懸念は「見えない不安」です。建物の劣化状態(特に配管や構造)が分かりにくく、購入後の修繕費用が予測しにくい点がリスク。
また、旧耐震基準の物件では、安全性を高めるための追加費用も必要になりがちです。
以下に新築のメリットとデメリットをまとめましたので、参考にしてみてください。
| 区分 | メリット(利点) | デメリット(懸念点) |
|---|---|---|
| 価格・費用 | ・物件価格が安い ・新築より初期費用を抑えられる |
・修繕費用がかかる ・リフォームや修繕が必要になる場合がある |
| 立地・環境 | ・好立地を選びやすい ・駅近や利便性の高い人気エリアの物件が多い |
・住宅性能が古い ・耐震性や断熱性が現行の基準に劣る場合があり、冬寒いなど生活の質に影響する |
| 自由度・状態 | ・リフォーム・リノベーションの自由度が高い ・費用をかけて自分好みの間取りやデザインにできる |
・設備が老朽化している ・水回りなどが古く、交換が必要になるリスクが高い |
| その他 | ・実物や周辺環境を確認できる ・購入後の資産価値の下落が緩やか |
・保証が短い ・売主が個人の場合、瑕疵担保責任の期間が新築に比べて短い(3ヶ月など) ・住宅ローン審査が厳しくなることがある |
【戸建て/マンション別】新築・中古どっちがいい?
こちらでは、戸建てとマンションそれぞれにおいて新築・中古どちらがいいのかを解説します。
戸建て編
戸建ての場合、「土地」と「建物」の両方を所有するため、建物の老朽化や修繕・リフォームの費用負担がダイレクトに所有者にかかる点が大きな特徴です。
以下の表で、新築戸建てと中古戸建ての比較をしましたので、参考にしてください。
| 比較項目 | 新築戸建て | 中古戸建て |
|---|---|---|
| 初期費用 | ・住宅ローン控除など税制優遇が手厚い | ・物件価格が圧倒的に安い(新築より1,000万円以上安いケースも多い) |
| 建物性能 | ・最新の耐震基準を満たし、断熱性が高く光熱費が抑えられる。 ・長期保証があり、入居後10年程度は大規模修繕不要 |
・リノベーションで性能改善や自由な間取り変更が可能 ・広い敷地の物件が多い傾向がある |
| リスク | ・購入直後に「新築プレミアム」が剥がれ、資産価値が大きく下落しやすい | ・建物の隠れた不具合のリスクがあり、購入前の調査が不可欠 |
| 立地 | ・新規開発地や郊外が中心 | ・駅近や人気エリアなど、生活基盤が整った好立地の選択肢が多い |
中古物件の隠れたリスクは、配管や構造に不具合があるケースも想定しておく必要があります。その際には、「ホームインスペクション」と呼ばれる、事前の調査を行なっておく必要があります。
- 新築が向く人: 最新の設備と高い安全・省エネ性能を求め、将来の修繕の心配をしたくない人
- 中古が向く人: 立地の良さを最優先し、リフォーム・リノベーションで自分好みの空間を安価に実現したい人
マンション編
マンションの場合、「共用部分の管理」や「修繕積立金」が選択の大きな鍵となります。特にランニングコストと管理体制に大きな違いが出ます。
以下の表で、新築戸建てと中古戸建ての比較をしましたので、参考にしてください。
| 比較項目 | 新築マンション | 中古マンション |
|---|---|---|
| 初期費用 | ・一般的に仲介手数料が不要なため、諸費用が中古より安い | ・物件価格が安い |
| ランニングコスト | ・当初の修繕積立金が低めに設定されていることが多い | ・修繕積立金が新築より高めに設定されていることが多い ・ランニングコストが高い |
| 管理・状態 | ・共用部・専有部ともに最新設備で保証も手厚い ・築後すぐの大規模修繕の心配がない |
・管理状況・修繕計画を事前に確認できる ・運営状態の良い物件を選べる ・実物を見られるため、日当たりや眺望の失敗がない |
| 立地 | ・大規模再開発エリアなど、未来の利便性を期待できる | ・流通量が多い ・利便性の高い好立地の選択肢が豊富 |
新築マンションは、大規模再開発エリアであれば、資産価値や未来の利便性を期待できる物件もあります。
一方で、中古マンションは、新築より数百万〜数千万円安いケースが多いです。また、駅や商業施設の近くなどの物件も見つけやすいのは中古マンションのメリットです。
- 新築が向く人: 資金に余裕があり、最新の設備、高いセキュリティ、そしてしばらくは維持費の変動を気にせず住みたい人
- 中古が向く人: 利便性の高い立地を最優先し、物件価格を抑えたい人。管理状態が良好な築浅〜築20年程度の物件を狙うのが賢明
中古+リノベーションという「第3の選択肢」もある
新築か中古かの二択に加えて、「中古+リノベーション」という第3の選択肢もあります。
「中古+リノベーション」は、中古物件のメリットを活かしつつ、新築のような自由度と快適性を手に入れる方法です。
「物件価格を抑えたい」「立地にこだわりたい」という中古のメリットと、「間取りやデザインを自由に決めたい」という新築・注文住宅のメリットを両立できます。
- 立地とデザインの自由度の両方を妥協したくない人
- 総予算を抑えつつオリジナルな住まいを作りたい人
- 手間と時間をかけられる人
- 物件の状態をしっかりチェックし、計画を進められる人
以下に中古+リノベーションのメリットとデメリットを表にしてまとめましたので、参考にしてみてください。
1. 中古+リノベーションのメリット
| 項目 | メリットの具体的内容 |
|---|---|
| 総額を抑えやすい | ・物件価格が安いため、リノベーションをしても新築より総額が抑えられるケースが多い |
| 好立地を選べる | ・新築物件が少ない駅近や人気の高い成熟したエリアでも物件を見つけやすい |
| 間取り・デザインが自由 | ・内装や水回り、壁の位置を変えるなど、間取りをゼロから設計できる ・ただし、マンションは構造上の制約あり |
| 物件を見てから計画できる | ・購入前に物件の周辺環境や日当たり、広さを確認できる ・確認した上で、リノベーション計画を立てられる |
| 資産価値が安定 | ・築年数が経っているため、購入後の価格下落が緩やか ・リノベーションにより物件価値が向上する効果もある |
中古+リノベーションのデメリットと注意点
| 項目 | デメリットと注意点 |
|---|---|
| 手間がかかる | ・「物件探し」と「リノベーション計画」を同時に進める必要がある ・入居までの期間も新築(建売)より長い。 |
| 隠れた不具合 | ・壁や床を剥がしてから、配管の老朽化や建物の劣化が見つかる場合がある ・追加費用が発生するリスクがある |
| ローンが複雑 | ・物件購入費とリノベーション費用をまとめて借りる「一体型ローン」を利用する必要がある ・金融機関を選ぶ必要がある |
| 性能改善の限界 | ・古い物件の場合、リノベーションをしても耐震性や断熱性を確保できない場合も |
新築と中古でローンや税制優遇制度が変わってくる
こちらでは、新築と中古でローンや税制優遇制度が変わってくるという点について解説します。
新築と中古の住宅ローン控除(減税)
住宅ローン控除(減税)は、国が省エネ住宅を優遇するため、新築が圧倒的に有利です。控除の「期間」と「借入限度額」になど、条件については、以下の表を参考にしてみてください。
| 項目 | 新築住宅(一般・省エネ) | 中古住宅(一般) |
|---|---|---|
| 控除期間 | 13年間 | 10年間 |
| 借入限度額 | 高い(環境性能で優遇、例:5,000万円など) | 原則 2,000万円 |
| 最大控除額 | 高い(総額で大きな差) | 低い |
| 適用要件 | 原則なし(2024年以降は省エネ基準必須) | 新耐震基準適合が必須 |
新築は最長13年間の控除を受けられ、省エネ性能が高いほど借入限度額が大きく上乗せされます。
一方、一般的な中古住宅は控除期間が10年と短く、借入限度額も原則2,000万円と低く設定されています。これにより、高額なローンを組んでも控除の恩恵をフルに受けられないことも。
中古住宅が控除を受けるには、新耐震基準に適合していることが必須です。
1982年1月1日以降の建築か、耐震基準適合証明書などで適合を証明できない場合、控除の対象外となるため、築古物件購入時は特に注意が必要です。
新築と中古、ローン審査の通りやすさ
新築と中古で申込者の属性審査基準は同じですが、「物件の担保評価」によりローン審査の通りやすさが異なります。結論として、新築の方が審査に有利です。
新築は購入価格が担保価値になりやすく、金融機関のリスクが低いと判断されます。
- 建物・設備が新品で資産価値が最大のため、金融機関の評価が高く、希望額の融資が通りやすい
- 法定耐用年数が最大のため、最長35年でローンを組める可能性が高く、月々の返済額が抑えられる
- 現行基準を満たすため、耐震性などで審査に落ちるリスクがほとんどない
一方で、中古は経年劣化により建物の担保価値が低く評価され、審査のハードルが上がります。
- 築年数に伴い評価が下がり、希望額の全額を借りられない可能性がある
- 自己資金(頭金)を多く要求される可能性がある
- 「法定耐用年数-築年数」で計算され、借入期間が短くなることもある
- 旧耐震基準(1981年5月以前)や再建築不可物件は、審査通過が難しくなる
ローン審査の通りやすさを比較しましたが、中古でも築浅物件を選んだり、耐震証明を取得したりすることで通ることが十分にあります。
リフォーム一体型ローンを利用することで、審査を有利に進められます。
家で迷ったら提携FPがいるオヒサマノイエへ相談ください!
新築・中古で最も重要なのは、物件価格だけではなく、税制優遇から維持費、ローンまで見据えた将来にわたる資金計画です。
特に中古やリノベーションには、見落としがちな諸費用や隠れた不具合のリスクが伴います。後悔しない家選びのため、まずは資金計画を固めましょう。
「自分に最適な予算は?」「住宅ローン控除を最大限活用したい」 そんな不安や疑問は、私たちオヒサマノイエにご相談ください。
弊社には、ファイナンシャルプランナーが在籍しています。お客様の将来のライフプランまで踏まえ、税制優遇を活かした最も無理のない最適な資金計画を無料でサポートします。
物件探しから資金計画までワンストップで支援し、安心の家づくりができますので、まずは以下のLINEやメール、電話からお気軽にお問い合わせください!
オヒサマノイエにご相談ください!
解決します。

注文住宅

リフォーム

リノベーション

自宅サウナ