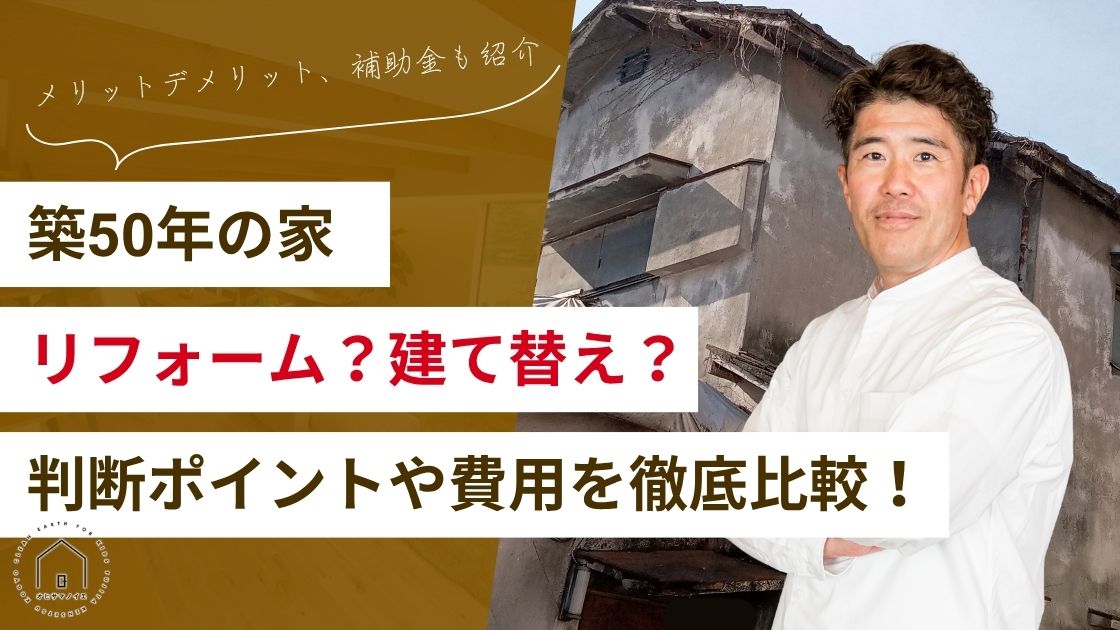この記事では、建物の地震に対する強さを示す「耐震等級」について、基礎知識から徹底的に解説します。
また、耐震等級がどのような基準で定められているのか、耐震性を調べる方法、耐震等級3を取得して後悔するポイントまで、深掘りしていきます。
2024年元旦に発生した能登半島地震では、多くの住宅が倒壊・損壊し、耐震性の重要性が改めて浮き彫りになりました。また、今後は南海トラフ地震が起こると言われています。
そんな中、「うちは大丈夫だろうか?」「耐震性能の高さは重要なの?」と、耐震性に不安を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事を読めば、「耐震等級3は意味がない」という疑問や、耐震等級に関する理解が深まりますので、安心できる住まいを実現するための参考にしてください。
オヒサマノイエにご相談ください!
解決します。

注文住宅

リフォーム

リノベーション

自宅サウナ

耐震等級とは:建物の耐震性能を表す指標
耐震等級とは、住宅性能表示制度によって定められている、建物の地震に対する強さを示す指標です。
耐震等級は、地震時の建物の倒壊や損傷のしにくさを以下の3段階で評価し、建物の耐震性能を客観的に判断できるようになっています。
- 耐震等級1
- 耐震等級2
- 耐震等級3
最も高いレベルが耐震等級3です。住宅の購入やリフォームを検討する際には、自身のライフスタイルや地域の地震リスクを考慮し、高い耐震等級の建物を選ぶことをおすすめします。
地震発生時の安心感はもちろん、地震後の生活の継続性や資産価値の維持にも役立ちます。適切な耐震等級の建物を選ぶことが、安全な住まいを実現するための鍵です。
耐震等級1〜3の基準

耐震等級は、2000年4月1日施行の「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づいて評価される、「住宅性能表示制度」内の項目のひとつです。
耐震等級は、「数百年に一度程度発生する極めて稀な大地震(震度6強から7程度)」と、「数十年に一度程度発生する稀な中規模地震(震度5程度)」でどれくらいの耐久性能を持つかが基準になります。
こちらでは、耐震等級1〜3の基準を解説します。
耐震等級1
耐震等級1とは、日本の建築基準法が定める最低限の耐震基準を満たしている性能です。耐震等級1の建物でも、建築基準法で定められた最低限の安全性を確保しているため、危険性が高いというわけではありません。
具体的には、以下の2つの基準を満たす耐震性があります。
- 震度6強から7程度に対して、建物が倒壊・崩壊しない
- 震度5程度に対して、建物が損傷しない
ここでいう「倒壊・崩壊しない」とは、人命が失われるような壊れ方はしない、という意味合いで、建物自体に大きな損傷が生じる可能性はあります。
しかし、より高い安全性を求める場合や、地震後の継続的な居住を重視する場合には、耐震等級2や3の建物を検討することが推奨されます。
耐震等級2
耐震等級2は、耐震等級1の1.25倍の耐震性能を持ちます。耐震等級2は、学校や病院など、災害時に避難所となる公共施設で求められる性能です。
耐震等級2の建物は、以下の基準を満たすとされています。
- 震度6強から7程度の1.25倍の力でも、建物が倒壊・崩壊しない
- 震度5程度の1.25倍の力でも、建物が損傷を生じない
耐震等級1では倒壊・崩壊しないものの大きな損傷が想定されるのに対し、耐震等級2では、損傷は生じるものの、補修を行えば居住できる可能性が高いです。
長期優良住宅として認定されるためには、原則として耐震等級2以上の耐震性能が求められます。木造2階建て住宅で壁量計算による場合は耐震等級3が求められるケースもあります。
耐震等級3
耐震等級3は、耐震性能の指標の中で、最も高いレベルです。消防署や警察署、避難所になるような重要な公共施設は、耐震等級3の性能を確保しています。
災害時にも機能を維持し、住民の安全を守る役割を果たす必要があるためです。耐震等級3の建物は、以下の基準を満たすとされています。
- 震度6強から7程度の1.5倍の力がかかっても、建物が倒壊・崩壊しない
- 震度5程度の1.5倍の力がかかっても、建物が損傷を生じない
耐震等級3は、南海トラフ地震のような大規模地震への備えとしても、非常に有効です。特に地震のリスクが高い地域での住宅建設や購入を検討する際には、耐震等級3を強く推奨します。
耐震等級を決める4つの要素
こちらでは、耐震等級を決める要素を4つ解説します。
建物の重さ
同じ耐震性能を持つ壁や柱、基礎があったとしても、建物が重ければ重いほど、地震時に建物にかかる慣性力(建物が揺れに抵抗しようとする力)が大きくなります。
これに比例して、耐震設備にかかる負担は大きく、結果として建物の耐震性は低下する傾向に。
逆に、建物を軽量化することで、地震時に建物に作用する力を軽減し、より少ない耐力壁や柱で高い耐震性を確保しやすくなります。
木造住宅が比較的耐震性を確保しやすいのは、鉄骨造やRC造に比べて軽いためです。
耐震設計においては、建物の構造や使用する材料を選定する際に、建物の重さを考慮し、バランスの取れた設計を行うことが重要になります。
耐力壁や柱の数
地震の際、建物にかかる大きな揺れの力を支えるのは、耐力壁や柱です。建物の規模や重さに対して、耐力壁や柱の数が十分に確保されているかどうかが、耐震性を大きく左右します。
耐力壁とは、地震や風などの横方向の力(水平力)に抵抗し、建物の変形を防ぐ役割を持つ、補強された壁のことです。
耐力壁は補強材を「筋交い」という手法で入れたり、「構造用合板」を張ったりすることで強度を高めます。柱も、柱は建物の垂直方向の重さを支える役割もはもちろん、耐力壁と一体となって水平力に抵抗します。
数が多いほど、地震力を分散して受け止めることができるため、建物全体の損傷を軽減し、倒壊を防ぐ効果が高まります。
耐力壁の配置
単に耐力壁の数が多ければ良いというわけではありません。建物全体にバランス良く耐力壁が配置されているかも重要です。
建築基準法では、耐震性を高めるために耐力壁を「釣合い良く配置しなければならない」と定められています。
東西南北の各方向に均等に配置することや、上階と下階の耐力壁の位置をできるだけ一致させる「直下率」の高さが求められます。
また、建物の重さの中心と強さの中心をできるだけ近づけることで、ねじれを抑え、地震でかかる力を受け流すことが可能です。そのため、より高い耐震性を実現できます。
基礎・床の耐震性
基礎は、建物の全重量を支え、地震時に地面から伝わる揺れの力を建物全体に伝える最初の部分です。基礎が弱いと、建物をしっかりと地面に固定できず、地震の揺れによる建物の傾きや沈下が起こってしまいます。
基礎と建物本体が一体となって揺れるよう「一体性」を高めることで、家自体が地震のエネルギーを効率的に吸収できるようになります。
一方、床は、「水平剛性」を高め、各階の耐力壁に地震力を均等に分配したり、建物のねじれを防いだりするためにも重要です。
床の剛性が低いと、地震力が特定の壁に集中してしまい、本来の耐震性能を発揮できなくなる可能性があります。強い床構造は、建物の耐震性を確保する上で不可欠な要素です。
耐震等級3の住宅を建てるメリット5選!
こちらでは、耐震等級3の住宅を建てるメリットを5つ紹介します。
災害時のダメージを抑えられる
耐震等級3の住宅は、耐震等級1や2の住宅と比較して、建物の揺れが大幅に軽減され、損傷も抑えられる点がメリットのひとつです。
具体的には、壁のひび割れや建具の歪みといった軽微な損傷で済み、補修なしでそのまま住み続けられる、あるいはごく簡単な修繕で済みます。
復旧にかかる時間や費用も最小限に抑えられるため、耐震等級3の住宅は、地震による人命の安全はもちろん、地震後の生活や、住宅も守ります。
地震後の生活再建がスムーズかつ早い
耐震等級3の住宅は、軽微な補修で済む、あるいは全く補修なしで住み続けられる可能性が高く、避難所生活や仮住まいへの移行といった、負担を回避できます。
耐震等級1や2の建物では、倒壊は免れても大規模な修繕が必要になったり、余震によるさらなる損傷で自宅に住めなくなったりするケースが少なくありません。
耐震等級3の住宅なら、生活サイクルが乱れることなく、地震後も比較的早く日常を取り戻せるため、精神的・経済的な損失を軽減できます。
住宅の資産価値が高くなる
耐震等級3の住宅は、地震による建物の損傷リスクが低いため、建物の物理的な劣化が抑えられます。万が一の災害時にも大規模な修繕費用がかかる可能性が低くなります。
地震に強いというのは、中古市場においても非常に高く評価される要素です。
買主は、安心できる家を求めるため、耐震性能が明確に証明されている耐震等級3の住宅は、より有利な条件で売却できる可能性が高くなります。
保険料の割引制度を受けられる
耐震等級3の住宅を建てるのは、災害時の安心感だけでなく、長期的な経済的負担の軽減できるのもメリットのひとつです。
耐震等級1の住宅では地震保険料が10%割引となるのに対し、耐震等級2では30%、そして耐震等級3の住宅では、50%もの割引が適用されます。
| 等級 | 割引率 |
|---|---|
| 耐震等級1 | 10% |
| 耐震等級2 | 30% |
| 耐震等級3 | 50% |
50%割引になれば、長期的に見れば数十万円単位の大きな節約になります。
住宅ローンの金利優遇を受けられる
耐震等級3の住宅は、通常よりも低い金利でローンを組むことができ、月々の返済額や総返済額を抑えられます。公的に高い品質と安全性を認められているため、金融機関側もリスクが低いと判断するためです。
例えば、長期固定金利住宅ローン「フラット35」において、「【フラット35】S(金利Aプラン)」という優遇制度の対象になります。
耐震等級3が対象になる【フラット35】S(金利Aプラン)や、耐震等級2が対象になる【フラット35】S(金利Bプラン)は【フラット35】と比較すると数十万円程度安くなります。
| プラン名 | 対象等級 |
|---|---|
| 【フラット35】S(金利Aプラン) | 耐震等級3 |
| 【フラット35】S(金利Bプラン) | 耐震等級2 |
住宅ローンの金利優遇を受けられるというのは耐震等級3の家を建てるメリットです。
【フラット35】なら、こどもがいる世帯や、夫婦や同姓パートナーのどちらかが40歳未満なら、「子育てプラス」というの優遇制度も別途使えます。
利用する住宅ローンの優遇制度に、耐震等級の優遇制度だけでなく、他にも優遇制度がないのかも含めて確認しておきましょう。
耐震等級3を取得するデメリット2選!
こちらでは、耐震等級3を取得してよくある後悔・デメリットを2つ紹介します。
壁・窓の位置が制限される
建物の重さの中心と強さの中心がずれないようにするために、耐力壁は偏りなく配置する必要があります。その結果、構造的に重要な位置に耐力壁が集中し、設計の自由度が低くなることも。
具体的には、以下のような制限が生じることがあります。
- 大きな開口部の制限がかかる場合がある
- 耐力壁のある場所には窓を設置できない
- 窓のサイズや位置が限定される
- 採光や通風、デザイン面で理想と異なる間取りになる
- 耐力壁は容易に移動できないため、リフォームの自由度が制限される
こういった制限は、デザイン性や開放感を重視する方にとっては、後悔のポイントになることも。耐震等級3を目指す場合は、事前に設計士と十分に相談し、デザインと耐震性のバランスについて理解しておくことが重要です。
建築費用が割高の割にメリットを感じない
地震が発生しなければ、耐震等級3の強さや安全性は「目に見えない安心」であるため、費用をかけた割にその恩恵を実感しにくいものです。
日常の生活において、建物の耐震性能を意識する機会はほとんどありません。
しかし、耐震等級3を実現するには、耐震等級1の住宅と比べて数十万円から数百万円程度の追加コストが発生します。こういった背景から、初期投資の大きさに比べてインパクトが薄く、無駄な出費だったのでは?と後悔する方も。
しかし、万が一の大地震が発生した際には、その真価が発揮され、人命と財産を守る上で大きなメリットとなるということを理解しておく必要があります。
【耐震等級別】よくある後悔
こちらでは、耐震等級1〜3、それぞれに家を建てた後に起こりうる後悔を、どういうことを抑えておけば後悔しにくいのかという対策も含めて解説します。
耐震等級1の場合
- 地震発生時に建物が損傷する不安
- 大規模な修繕・建て替えが必要になる不安
- 家族の安全への懸念
上記のような後悔をするようであれば、再度、耐震等級3への対応、制震装置の導入、耐火建築物の仕様にするといった対策もできますが、あまり現実的ではないでしょう。
地震保険に加入して経済的に備えるなどの対策をすると良いです。
また、家族への安全のためには、ハザードマップや、防災意識の共有など、地震発生時に身を守る行動ができるようにしておくことをおすすめします。
耐震等級2の場合
- いっそのこと耐震等級3にしたらよかった
- ローンや保険の優遇制度の恩恵をもっと受けたかった
- 売却時、「もっと上」を求める買い手から敬遠された
耐震等級2にして後悔される方は、あまり多くはありません。耐震等級2にして後悔することとしてあえて挙げるなら、いっそのこと耐震等級3にしておいたらよかったというもの。
対策として、売却の際に、耐震等級3の方が買い手がつきやすいことと、ローンや保険の優遇制度の内容は納得できるかということを抑えておきましょう。
耐震等級3の場合
- ”耐震等級3”だと思ったら”耐震等級3相当”だった
- 建築にかかる費用が割高だった
- 普段は耐震等級3の恩恵を感じない
耐震等級3相当は耐震等級3と同等の耐震性能を持っているものの、正式な認定を受けていない住宅のことを指します。
耐震等級3であることを証明するためにも、評価を受ける必要がありますが、費用がかかってしまいます。さらに、耐震等級3相当であれば、保険やローンの割引が適用されないケースも。
耐震等級3相当なのか、耐震等級3という正式な認定を受けているのかはチェックしておきましょう。
「耐震等級3は意味ない」「耐震等級1でも十分」と言われる理由
耐震等級を検討する際には、「耐震等級3は意味ない」「耐震等級1でも十分」と言う声もよく見られます。こちらでは、そう言われる理由を2つ解説します。
倒壊や損壊を必ず防げるわけではないから
「耐震等級3は意味ない」「耐震等級1でも十分」という意見が出る理由に、「倒壊や損壊を必ず防げるわけではないから」という考え方があります。
耐震等級3の建物であっても、「絶対に倒壊しない」「どんな地震でも無傷である」と100%言い切れるものではありません。
想定をはるかに超える巨大地震や、連続して発生する群発地震、津波や液状化といったさまざまな災害要因で、住宅に被害を受けることがあります。
しかし、耐震等級3は、熊本地震などの実際の地震被害データを見ても、効果は明らかで、耐震等級3の建物は、ほとんどが無被害か軽微な損傷で済んでいます。
以下は、国土交通省の報告ですが、耐震等級3であれば、熊本地震でも無被害であることが示されています。
- 旧耐震基準と新耐震基準の木造建築物の倒壊率に顕著な差があったのは、新耐震基準は旧耐震基準の約1.4倍の壁量が確保されているためと考えられる。
- なお、住宅性能表示制度による耐震等級3(倒壊等防止)の住宅は新耐震基準の約1.5倍の壁量が確保されており、これに該当するものは、大きな損傷が見られず、大部分が無被害であった。
地震対策も必要だから
「耐震等級3は意味ない」「耐震等級1でも十分」という意見の中には、「建物の耐震性だけでなく、その他の地震対策も重要だから」という考え方があります。
いくら建物自体が頑丈にできていても、地盤が弱ければ地震の影響を受けてしまいます。液状化しやすい地盤であれば、建物が傾いたり沈下したりする可能性があり、耐震等級が高くても被害を避けられません。
そのため、建物を建てる前の地盤調査と、必要に応じた地盤改良が、耐震等級と同様に不可欠な地震対策になります。
また、家具の転倒防止対策、窓ガラスの飛散防止フィルム、火災報知器の設置など、内部対策も必要です。
耐震等級・耐震性の調べ方
こちらでは、耐震等級・耐震性の調べ方を解説します。
住宅性能評価書を確認する
住宅性能評価書は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づき、国土交通大臣から指定を受けた第三者機関が、住宅の性能を評価を記載した公的な書類です。
評価書には、耐震性だけでなく、省エネルギー性、劣化の軽減、維持管理・更新への配慮など、全部で10分野の評価項目があり、等級や数値で表示されています。
住宅性能評価書の中でも、「構造の安定」という大項目の中の、「耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)」という項目に表示されます。
一方、中古住宅の場合、売主や不動産会社に、住宅性能評価書があるか確認します。「既存住宅性能評価書」があれば、現在の耐震性能を把握できます。
もし評価書がない場合でも、建築時の「設計住宅性能評価書」や「建設住宅性能評価書」がないかもチェックしてみてください。
第三者機関から住宅性能の評価を受ける
ここでいう第三者機関とは、国土交通大臣から指定を受けた「登録住宅性能評価機関」のことです。
第三者機関は、住宅の設計図書や実際の工事現場を検査し、専門的な知見に基づいて住宅の性能を公正に評価します。建築会社や売主とは独立した立場であるため、その評価結果は非常に高い信頼性があるのが特徴です。
建築会社が自社で「耐震等級3相当」と謳っていても、それが客観的な基準に基づいているか、実際にその性能が確保されているかは、一般の方には判断が難しいものです。
評価結果の信頼性が非常に高いため、第三者機関の評価を受けて、耐震性能を確認するのも良いでしょう。評価書の取得するには、およそ10〜20万円ほどかかります。
耐震診断を受ける
耐震診断とは、建築士などの専門家が、建物の構造や地盤、基礎、壁、柱、屋根などを調査し、耐震性能がどの程度あるかを評価することです。
耐震診断は、建築事務所、工務店、または各地方自治体が指定する耐震診断士などに依頼することで診断を受けられます。また、自己診断ツールを使用することでも診断が可能です。
耐震診断は、築年数が古い住宅や、住宅性能評価書がない場合など、現在の建物の耐震性能を正確に把握するために非常に有効です。
主に以下のような住宅にお住まいであれば、耐震診断を受けることをおすすめします。
- 旧耐震基準(1981年5月31日以前)で建築確認申請が受理された建物
- 住宅性能評価書がない建物
- 大規模なリフォームを検討している建物
耐震診断は費用がかかりますが、いざという時の安心と、今後の住宅に関する計画を立てる上での重要な情報源となるため、検討する価値があるでしょう。
耐震等級を上げたいときの依頼方法
こちらでは、耐震等級を上げたいときの依頼方法を解説します。
新築注文住宅なら設計時に希望を伝える
耐震等級を上げたい場合、新築の注文住宅であれば、設計の初期段階でその希望を伝える必要があるケースが多いです。
注文住宅の設計のヒアリング段階で、「耐震等級3がいい」「耐震性の高くしたい」という希望を伝えれば、耐震等級を上げる前提でプランニングをしてくれます。
もし設計が進んだ後や工事が始まってから耐震等級の変更を希望すると、設計のやり直しや工事の遅延、大幅な追加費用が発生してしまいます。
オヒサマノイエでは、耐震等級3が標準です。より高い耐震性を求める方は、ヒアリングの際に希望をお聞かせください。
建売や中古なら耐震性を強化する
既存住宅であっても、耐震等級を向上させることは可能です。一般的に「耐震改修」や「耐震リフォーム」と呼ばれる補強工事が行われます。
まずは、専門の建築士等による「耐震診断」を受けてください。耐震診断の結果に基づき、建物の状態や目指す耐震等級に応じて、以下の補強工事を行います。
- 基礎の補強
- 耐力壁の増設・強化
- 接合部の補強
- 屋根の軽量化
- 制震装置の導入
建売や中古住宅の耐震性を強化するには、専門知識と費用が必要ですが、安全な住まいを確保し、将来の安心を手に入れるための重要な投資です。まずは信頼できる耐震診断の専門家に相談することから始めましょう。
住宅の耐震等級を高めるなら「オヒサマノイエ」へ!
ただ単に耐震等級3を取得するだけでなく、本当の意味で安心できる家づくりをするなら、ぜひ「オヒサマノイエ」にご相談ください。
オヒサマノイエで建てる家は、最高等級である耐震等級3を標準仕様としています。また、年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロ以下にすることを目指した「ZEH住宅」です。
建物の重さを最小限に抑えつつ、強度と配置のバランスを徹底的に追求した耐力壁計画、そして建物を支える基礎と床の水平剛性にも一切妥協しません。
さらに、要望に応じて制震ダンパーなどの先進技術も積極的に取り入れ、揺れをさらに吸収するプラスαの安全性を追求。
しかし、耐震性を高めるだけでなく、ライフスタイルやデザインの要望を丁寧にヒアリングしながら、利便性や快適性を高めるための最適なプランをご提案いたします。
間取りの自由度と耐震性を両立させるための知識と経験が、オヒサマノイエにはあります。
地震大国日本で、長く快適に、かつ安全に暮らせる高性能な住まいを「オヒサマノイエ」で実現しませんか? 疑問や家づくりの夢をお聞かせください。
オヒサマノイエにご相談ください!
解決します。

注文住宅

リフォーム

リノベーション

自宅サウナ